子ども体験講座 日本の文化「茶の湯」を体験
ページ番号 461-575-567
最終更新日 2022年3月28日
谷戸公民館 和室で 令和4年2月19日 日本の文化「茶の湯」を体験しました。
講師
高橋 宗啓:裏千家 茶道講師
場所
谷戸公民館 和室
内容
1.和室への入り方
2.和室での正座でのおじぎのしかた
3.茶道の歴史と心
4.お茶室での作法
5.お菓子の頂き方
6.お茶のたて方
7.お茶椀の持ち方といただき方
8.DVD「お茶会に招かれて」を視聴
講師から、掛け軸「和敬清寂」
「茶道で、主人と客が互いの心を和らげてつつしみ敬い、茶室の品々や雰囲気を清浄な状態に保つこと」
などの詳しい説明

「和顔愛語」とは、「和やかな顔と思いやりの言葉で人に接」すること。

風炉釜のと建水、水差し、の配置

亭主のお点前「和敬清寂」の 「清」の意味がある
講師からお辞儀の仕方
いらっしゃいませ、よろしくおねがいしますのお辞儀

つくしとさくら
お菓子をじっくり確認する
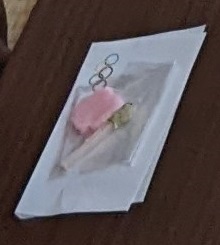
懐紙にのせたお干菓子「つくしとさくら」
お菓子は、食べやすい大きさに切っ足り、割ったり、一口づついただくことを教わりました。
茶筅を使ってお茶をたてる様子

お茶の頂き方を教わる

お茶の頂き方を教わる
1 茶碗を膝の前において、亭主(ホスト)に「お点前ちょうだいします」とお辞儀をして挨拶。
2 茶碗を左手の平の上にしっかりと載せ、右手を添えて感謝の気持ちを込めておしいただくこと教わりました。
3 茶碗の正面でいただくことを避けるため右手で手前に2度まわして
静かに味わいながらいただき、最後の一口は、音を立てて吸いきることを教わりました。
※当日は、作法のみで、飲食はしていません。
参加者の感想から
・お茶の歴史が知れて、マナーも知れて良かった。(小5)
・形だけでなく、茶道に取り組み心まで教えていただけた。(小6)
・なにも知らなかったけど、分かるようになった。(小5)
・自分で体験しながら学習できた。(小6)
・とてもたのしかったです。べんきょうになりました。(小2)
・今度お茶をたてた後、そのばで飲んでみたいです。(小2)
・安土桃山時代に千利休が始めて400年たっても子孫にも
茶道を受け継がれていてすごかったです。 (小3)
・お茶のたて方が分かってとても楽しかったです(小2)
・おじぎをするのがはずかしかったです。(小1)
おちゃをつくるのが思ってたよりたのしかった。
かしゃかしゃ上手にできました。
