食中毒の予防
ページ番号 425-407-234
最終更新日 2025年7月7日
「腸管出血性大腸菌(O157、O111)」「ノロウイルス」などの名前を聞いたことがあると思います。
目には見えませんが、様々な食中毒菌やウイルスが、手や包丁・まな板・食品などから感染しています。また人から人への感染もあります。
食中毒にかかると、様々な症状があらわれ、ときには生命にかかわることもあります。
高温多湿の季節は、特に食中毒の予防や、感染後の正しい対応のために、正しい知識を身につけ、食中毒を予防しましょう。
- 食中毒とは
- 食中毒の原因
- 手洗いのポイント
- 買い物のポイント
- 冷蔵庫・冷凍庫に保存するときのポイント
- 調理のときのポイント
- 台所を清潔にするポイント
- 食中毒が疑われるときは医療機関へ
- 食中毒を起こしたときの応急対応
- 二次感染を防ぐために
- 集団感染が疑われるときは
- からだの抵抗力を高める
食中毒とは

食中毒は、細菌やウイルス、ふぐの肝、毒きのこなどの有毒物を飲食することによって起こります。
腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの急性胃腸炎の症状や、しびれや麻痺などの神経障害などが代表な症状です。
ときには生命にかかわることもあり、注意が必要です。
食中毒の原因
| 原因菌・ウイルス | 潜伏期間 | 症状 | 感染源 |
|---|---|---|---|
| サルモネラ属菌 | 5時間から72時間、平均12時間 | 下痢、腹痛、悪寒、発熱、嘔吐、頭痛など | 鶏卵・食肉およびその加工品など |
| 腸炎ビブリオ | 10時間から24時間 | 差し込むような腹痛、激しい下痢 | 魚介類など |
| カンピロバクター | 2日から7日、 平均2日から3日 |
発熱、倦怠感、筋肉痛に続いて、吐き気、下痢 | 鶏肉など |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 3日から5日 | 激しい腹痛、血便(鮮血)のほか、合併症を起こす | 食肉など |
| 黄色ブドウ球菌 | 1時間から5時間、 平均3時間 |
吐き気、嘔吐、下痢、腹痛 | 弁当、おにぎりなど |
| ウェルシュ菌 | 6時間から18時間、 平均12時間 |
下痢、軽い腹痛 | 食肉・魚介類など |
| ノロウイルス | 1日から2日 | 嘔吐、腹痛、下痢、頭痛、発熱など | 二枚貝全般、調理者の手を介した食品など |
手洗いのポイント
手には目に見えない菌がついています。調理や食事前、トイレの後、肉や魚などの生ものを触った後、外出から帰ったときなど、せっけんで手をしっかり洗いましょう。
汚れた手で触った蛇口も、手についたせっけんで洗ってから、手と一緒に漱ぎましょう。
買い物のポイント
- 生鮮食品は新鮮なものを選ぶ。
- 食品は新しいものを選ぶ。
- 生鮮食品や冷蔵・冷凍食品は最後に買う。
- 買い物の後は寄り道せずにすぐに持ち帰る。
- 買い物が終わったらすぐに冷蔵庫・冷凍庫に入れる。
冷蔵庫・冷凍庫に保存するときのポイント
- 冷蔵庫や冷凍庫は容量の7割を目安にして、詰めすぎない。
- 冷蔵庫の温度は10度以下に、冷凍庫はマイナス15度以下を維持する。(多くの細菌の増殖は10度以下で遅くなり、0度以下で停止する。ただしマイナス15度以下でも死滅するわけではないので早めに使いきる。)
- 肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の食品に汁がかからないようにする。
- 温かい食品は冷ましてから入れる。
- ドアの開閉はできるだけ早く、回数を少なくする。
- 一度解凍したものは再び冷凍しない。
調理のときのポイント
- 加熱調理の際は十分に加熱する。(食品の中心部が75度以上、1分以上の加熱が目安)
- 厚い肉や魚の姿焼きなどは切れ目を入れ、中まで火を通す。
- 調理を中断するときは室温に放置せず、冷蔵庫に保管する。
- 電子レンジで調理をする際は、ときどきかき混ぜる。
- 魚、野菜などは流水でしっかりと洗う。
- ひび割れた卵の使用は避け、溶き卵はすぐ使い、卵を使った容器は必ず洗ってから次の食品に使う。
台所を清潔にするポイント

ふきん
熱湯や塩素系漂白剤で消毒し、十分に乾燥させてから使う。
まな板
野菜・調理済み食品用と生肉・魚用の2枚あるとよい。
包丁
柄の部分、刃の付け根も丁寧に洗う。
スポンジ・たわし
よくすすいで洗剤を落とし、よく乾かす。
調理台
物を置きっぱなしにしない。
食中毒が疑われるときは医療機関へ
吐き気や嘔吐、下痢、発熱、腹痛などの症状があらわれたら食中毒の場合があります。
同じ食事をした人に同様な症状があれば、食中毒の疑いが高くなります。自己判断せず、すみやかに医師に相談することが大切です。
食中毒を起こしたときの応急対応
- 脱水症状にならないように水分を十分にとり、早めに受診する。
- 自己判断で下痢止めや風邪薬などの市販薬を飲まない。
- 安静にする。
二次感染を防ぐために
- 患者はシャワーのみに。入浴するなら一番最後に入る。
- 手洗いをこまめに行う。(逆性せっけん、消毒用アルコールや塩素系消毒薬で消毒)
- 患者の吐いたものや便は、使い捨ての手袋やマスクを用いて処理する。
- 下着などは家族とは別に洗濯して、日光で乾かす。
- 患者が使用した食器は、洗剤でよく洗い、流水で十分にすすいだ後、漂白剤に1時間以上ひたす。
集団感染が疑われるときは
- 複数の患者が出ているときは医師や保健所に相談する。
- 吐いたものや原因と思われる食品は、ビニール袋などに入れて医師に見せる。
- 食品が残っていないときは、空の容器、買った店のレシート、包装紙などを保管しておく。
からだの抵抗力を高める
同じものを食べても食中毒を起こす人とそうでない人がいるのは、その人の抵抗力や免疫力の違いです。
日頃からいろんなものをバランスよく食べ、暴飲暴食をせずに、丈夫なからだをつくることです。
そのためには、ヨーグルトやみそ、納豆などの発酵食品や野菜・海藻・果物・きのこや穀物などの食物繊維やビタミン・ミネラルを十分にとって腸内細菌の働きを活性化するなど、からだの防衛力を高めておくことが大切です。
またストレスや慢性疲労は免疫力を低下させます。規則正しい生活を心がけましょう。

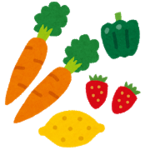
関連リンク
東京都保健医療局「食品衛生の窓」で食中毒発生状況を発表しています
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、健康課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-439-3526
ファクス:042-422-7309
