2025年9月1日号NO.612
ページ番号 214-178-691
最終更新日 2025年8月28日
目次
市報そのまま
電子書籍で閲覧
市報を「TAMA ebooks(タマイーブックス)![]() 」で電子書籍として閲覧できます。
」で電子書籍として閲覧できます。
(注記)発行日から概ね1週間後に閲覧できるようになります。
全ページダウンロード
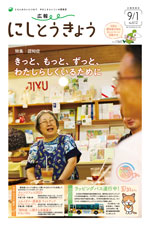
ページごとダウンロード
特集「認知症」 きっと、もっと、ずっと、わたしらしくいるために
あんしん暮らし情報/市税の休日・夜間納付相談窓口|手話通訳者登録試験(手話通訳者全国統一試験)|高齢者肺炎球菌予防接種|一般コミュニティ助成事業のご案内|野焼き・小型焼却炉による焼却行為は原則禁止です|おくやみ窓口をご利用ください|リフォーム業者をあっせんします!|9月27日(土)の土曜日窓口はマイナンバー関連の手続ができません|災害時の断水に備えましょう!|保育園保育推進員|はなバス 車体広告|市民スポーツまつり フリーマーケット出店者|寄附|9月の人権・身の上相談のご案内
審議会など|9月は自殺対策強化月間|第2回胸部健診(肺がん・結核)|健康ポイントアプリ「あるこ」三市合同ウオークラリー 参加登録受付中!|休日診療|電話相談
無料市民相談|女性を狙った犯罪に注意|まちづくりに関する説明会|国勢調査2025はじまります!
9月は高齢者悪質商法被害防止 共同キャンペーン月間|指定寄附資金募集「自走式水洗トイレカー」のクラウドファンディングにご協力をお願いします|みんなの伝言板|他機関からのお知らせ
特集「認知症」 それぞれの視点から、認知症を知る|数字から、認知症を知る|正しい理解で、認知症を知る
のびのび子育て/お口の健康相談室|3~4カ月児健康診査|1歳児講座|2歳児相談会|3歳児健康診査|離乳食講習会スタート|ファミリー学級・2日制 第8コース 初めて父親・母親になる方のための教室|個別育児相談会|ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談|乳・子・青 医療証の送付について|重症心身障害児(者)通所事業(医療型)の新規利用希望者の受付を開始|給食費補助金の交付|ファミリー・サポート・センター ファミリー会員登録説明会|先輩ママとお話する会|保護者助成金の支給
ようこそとしょかん9月|いきいきシニア/敬老金などを贈呈|健康体操教室(後期)・各種教室
いきいきシニア/9月から高齢者生活状況調査を実施|初めての方対象 フレイルチェックを受けてみよう!|障害のある方へ/ペアレントメンターとお話会|わくわく催し/認知症サポーター養成講座|早稲田スポーツフェスタin 東伏見|薬物乱用防止ポスター・標語展|女性のための腹筋・ヒップアップトレーニング(保育あり)|生活習慣病予防講演会「知っておきたい大腸がんのこと 生活習慣の見直しと予防のポイントについて」|命を守る一人ひとりの防災対策 ローリングストックと災害時に役立つパッククッキング|防災まち歩き 田無神社と田無用水をめぐる|事業承継個別相談会|しゃきしゃき体操パート1講座
わくわく催し/パリテ講座 わが子らしさが輝きだす、あたたかい育て方の秘訣|保育園合同就職フェア|住宅の電力を自給自足する! 太陽光発電と蓄電設備の話|障害者サポーター養成講座(初級編)|日本語スピーチコンテスト2025|就職支援セミナー|多摩六都フェア 水と緑ウオッチングウオーク|西東京市くらしヘルパー養成研修(全2日)|市民体力テスト|西東京市図書館講演会 “ふつうの体”はどうできている? 細胞と分子から見るからだのしくみ|ピースウオーク
少年サッカー大会 参加チーム募集|二十歳のつどい|市民文化祭 PRイベント開催|多摩六都科学館ナビ|多摩北部広域子ども体験塾 たまろく恐竜ラボ きみも博士だ!恐竜調査に乗りだそう!
特集「認知症」インタビュー
当事者
藤島岳彦さん
いま一番楽しいことは、認知症に関する講演や当事者との交流活動です。病気などで会社を辞めると、人や社会とのつながりが希薄になります。でも、病気になっても、このようにいろいろな機会をいただくことで、絶えずコミュニケーションができ、多くの人とのつながりが持てていることに感謝しています。
病気に気づいたのは、以前勤めていた会社で「様子がおかしいから病院に行け」と言われたことです。長年、営業職をしていて、会った人の名前を覚えることが得意でした。でも、新規顧客の名前を覚えられない、約束した日時を忘れる、会議で話した内容を覚えていないなど、今までの自分では考えられないミスを指摘されることが続いていました。
この時は心無い言葉に思えましたが、いま思うと、やさしく言われていたら検査を受けに行っていないですね。令和4年に病院に行くと、鬱病と診断されました。
ただ…ネクタイの締め方が分からなくなったり、鍵を閉めたか忘れてしまい何度も何度も確認することが増えたり、鬱とは違う違和感を覚えることが多くなって。脳神経科で再度検査を受けると、若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。
結局、勤めている会社は依願退職をしてほしいと迫られ、実質クビに。まだまだ認知症に関する理解がない社会だと実感しました。認知症と知ってどう思ったかをよく聞かれますが「しょうがない」の一言。
もちろん不安がないわけではないですが、認知症に限らず他の病気でも、それに対応するしかない。なので、なってしまったものは仕方ない、その病気とどう付き合っていくかだと思っています。
もちろん、忘れてしまう不安はあるので、スマホのメモ機能は手放せません。
常に、話したことや大事なことは全てメモします。メモしたことを忘れても、次の日もメモを開くと前の記録を見るので覚えていなくてもいい。ちゃんと対処できていれば大丈夫なんです !
今は介護ホームで、クリーンスタッフとして週に4日働いています。
職場の人たちも、わたしの状況を理解してくれているので、とても働きやすい環境です。
昔より、今のほうが生活の質がいい気さえします。
身の回りのことはできるし、工夫することでできるようになることもたくさんある。認知症ではない人と同じように、新しいことにチャレンジすることもできています。
たくさんの人と出会い、仲間がいて、好きなことをして生活できている。
お金で買えない時間を過ごせているので、生活の質がいいと自分では思っているんです。
「病気とわかるのが怖い」と検査を受けない人や、病院に行かない人がいますが、自分にとって大事なことを見逃してしまいます。どんな病気も、早期発見と正確な診断が重要。
早期に正しい診断を受ければ、予防や治療の幅も広くなります。
認知症は、健康で運動能力があれば、早期発見により回復したり、軽度であれば進行を遅らせたりすることができる病気でもあります。この軽度の時を見逃してしまうのはもったいないと思いませんか?早く知れば、その分、治療に充てる時間も長くなります。 私は早期に気づき、正しい対処ができていることで、いまは普通に生活ができています。
検査も病院も怖くないということを体現し、時間を無駄にしないためにも、勇気をもって検診を受けてほしいと伝えていきたいですね。
そのために、多くの講演をお引き受けし、名前を出して活動をしています。
先日は、NHKの番組の認知症新時代というテーマの放送回に、当事者として出演しました。こうして話をする機会が増えると、多くの方に「どうしたらずっとポジティブでいられるのか」と聞かれます。私としてはポジティブにしようと考えることはなくて…自分らしくいること、自分がやりたいことをすることで、周囲からはそう見えるみたいです。
自分が普通にしていることで、勇気や元気をもらえると言ってくれる人がたくさんいることに感謝です。
本人ミーティングの様子
西東京市では本人ミーティングが毎月1回開催されています。
仕事があると最初から参加できないこともありますが、みなさんにも会いたいので、少しでも参加するようにしています。仲間に会えば元気になるし、とにかく楽しい。
いま悩んでいる人に、外に出て、同志をつくり、声を出そうよと伝えたい。
家族には、一緒に来てみてと。
認知症のある人の代弁をし、誰もが安心して暮らせる社会を一緒につくってければと思います。
家族
八重樫達也さん
最初に妻の異変に気付いたのは、令和2年2月頃。当時、居酒屋を経営していましたが、妻は体調がすぐれない日が続き店には出られず、食事も摂れずに衰弱し、精神的にも不安定になっていきました。
このままでは本当にすべてが立ち行かなくなると思い、西東京市の健康相談に電話をしました。状況を話すと、すぐに保健師さん2人が自宅に来てくれました。いま思うと当然なのですが、即入院でした。しかも、本人や家族が退院したいといっても、症状の改善と医師の判断がなければ退院できないと知って、こんなに大変なことになっているのだと、改めて愕然としました。
あのときに、市役所に相談してよかった。保健師のお二人にも本当に感謝しています。だれにも相談しなかったら…妻の命が危なかったかもしれないし、今日はなかったかもしれません。
このときの診断は「鬱」でした。しかし、治療を続けても、日常的にできないことが増え、様々な自律神経症状にも悩まされ始め、こうした変化に、すごく違和感がありました。治療を始めてから約2年が過ぎた頃、「本当に鬱なのか?違うのでは?」という思いが強くなりました。自分なりに調べたり、周囲の人に話を聞いたりして、レビー小体型の認知症なのではないかと考えるようになっていました。
心療内科の主治医に意思を伝え、専門医の元で認知症の検査を受けました。
スコアは認知症の可能性を示唆しており、精密検査の結果、若年性レビー小体型認知症であることが分かりました。この頃、妻はさまざまな症状を抱え、ほぼ寝たきりで、家から出ることができない状態でした。
妻が元気になるきっかけの一つは、地域包括支援センターの職員の方が勧めてくれた西東京市認知症予防プログラムです。週に1回、全7回通うプログラムでした。プログラム初日は本調子ではなく、万が一のためにと、スタッフに妻の状況を詳細に共有しました。そして数時間後、こちらの不安をよそに妻は嬉しそうに笑顔で帰ってきました。
それから7回、体調のよい日ばかりではなかったのですが、毎週通うことができました。これが大きな自信につながり、そこから明らかに回復していくのが分かりました。笑顔も会話も増え、外に出る機会も多くなりました。誰かと話し、つながることが、こんなにも大事なことなのだと痛感しています。月1回開催される西東京市の認知症本人ミーティングは、妻の楽しみの場の一つでもあります。
仲間と集まり、一緒にお茶を楽しむ。この何でもない日常は、妻にとって社会とつながる大事なことなんです。
妻の体力は回復していますが、認知症による、もの忘れはもちろんあります。
「忘れてしまうけど、思い出せばいい」と思えるようになってから、とても気持ちが楽になったようです。妻は毎日ノートの1ページいっぱいに、メモを書いています。その日あったこと、覚えておきたいこと、楽しかったことなど、とにかく何でも書く。そのメモがあれば、たとえ忘れても書いた文字まで消えてしまうわけではないから、読み返せばいいんです。
丹野智文さんの実話をもとにつくられた映画「オレンジ・ランプ」を観て、「人生をあきらめなくてもいい」というメッセージにも本当に勇気をもらいました。
認知症になると「忘れる」ということが恐怖に感じます。
本人もですが、家族も同じ。私は、妻が困らないように、嫌な思いをしないようにと、常に先回りして、何でもやってしまっていました。あの頃の私は、できることまで取り上げ、できるようになるための機会まで取り上げていたのだと思います。
いまは、妻の得意なこと、やりたいことはやってもらい、苦手なことは私がするようにして、いまを楽しく生きています。例えば、妻はお皿を洗うのが得意ですが、それを食器棚に片づけるのが苦手。どこに戻せばいいか分からなくなり、その分からない感覚が不安を呼びおこします。でも、それぞれが得意な部分を分担すれば、問題のないこと。これは、認知症じゃなくても同じですよね。全部一人でできなければいけないわけじゃない。ともに歩むとは、お互いが助け合い生きることですから。
認知症になっても全てできなくなるわけではなく、人生をあきらめる必要はない。ほんの少し不便なことが増えるので、一人ではなくみんなで支え合えばほがらかに生きていくことができます。
まずは専門医に相談することが大事です。
鬱とレビー小体型認知症は、初期の症状はとても似ていて見分けがつきにくく、認知症の専門医でなければ気づかないことも多いといわれています。
専門医に診てもらったことで多くのことが分かり、納得し、すっきりしました。
そして、不安に思ったら、専門医に加えて市役所、地域の相談支援窓口にも相談をしてみてほしいです。
最後に何より大事なのは外に出て地域とつながり、誰かと話すこと。認知症があることは、決して恥ずかしいことではありません。地域社会の中で必要な手助けを得ながら全てをあきらめるようなことなく笑顔で生きていくことが可能だと信じたい。みんなでつながりましょうと伝え続けていきたいです。
医師 西東京市医師会会長
令和6年9月15日号でMCI(軽度認知障害)について教えていただいた、西東京市医師会会長 三輪 隆子先生に、今回は早期に気づくポイントをお聞きしました。
プロフィール
認定内科医 神経内科専門医 とうきょうオレンジドクター(注釈1)
身体障害指定医(肢体不自由、音声言語、平衡機能障害)
静岡県清水市(現静岡市清水区)出身。昭和59年信州大学卒業後、信州大学第3 内科入局。佐久総合病院、東京都立神経病院、狭山神経内科病院などにて、神経疾患、難病の診療に従事。平成7 年国立身体障害者リハビリテーション病院 神経内科医長に就任。
平成19年1月西東京市下保谷にて「みわ内科クリニック」を開院。
令和5年6月より西東京市医師会医師会会長に就任。
(注釈1)「とうきょうオレンジドクター」とは
都内に勤務し、地域包括支援センターなどの地域の関係機関と連携して活動できる、東京都が認定する認知症サポート医です。
年齢によるもの忘れと、MCI(軽度認知障害)の違いを教えてください
年齢によるもの忘れが、昨日の夕食のメニューや会話を忘れるのに対して、MCI の人は夕食を食べたことが記憶されず覚えていない状態です。このように、過去の出来事を経験した出来事そのものだけでなく、時間や場所、感情といった付随情報も一緒に記憶されます。これを専門的にはエピソード記憶と言います。MCIや認知症では、このエピソード記憶が障害されます。そのため、MCIでは、体験が、「記憶されない」ことが起こります。ビデオのスイッチが入っていないような状態。忘れるのではなく、そもそも記憶されていません。何回も同じことを聞くのは、その事柄や行動自体が記憶されていないからです。
年齢によるもの忘れは、記憶はできている状態で、部分的に記憶があいまいな状態です。
MCI に早く気づくポイントはありますか?
もの忘れが気になったら、少し具体的に見てほしいです。歳のせいだから仕方がないと放置していると、MCI の兆候まで見逃すことになります。
認知機能の低下が進みMCI や軽度認知症になると、スポット的に記憶されないことが増えていきます。このため、周囲から何度か「全く記憶にないこと」の指摘を受けるようであれば、MCI もしくは認知症に進みやすい要注意の状態なので、専門医に相談するのがいいですね。
基本は、かかりつけ医に相談していただくのがいいのですが、注意すべき点もあります。
私は認知症の専門医でもありますが、長年診ている患者さんの異変に気付かないことがあります。なぜなら、MCI の段階では、過去の記憶はしっかりあり、長年やり続けていることは、今まで通りにできるからです。
通い慣れた病院での受付や診察室への出入り、慣れた先生との会話には何の問題も起こらないケースがほとんどです。日常生活で慣れていることには問題がないので、気づくのが遅れるのだと思います。
しかし、「新しいこと」は全く記憶されないことが起こります。
最近では、コロナ禍でこれが顕著になりました。新型コロナワクチン接種が始まり、今までと違う用紙の記入や受診券の提出などが明らかにできないことでMCI に気づく方が何人もいました。最近だと、保険証の切り替えですね。新しいマイナ保険証が記憶されない。見たことない、持っていない、知らないなど。これにより、医師よりも受付のスタッフが異変に気付くこともあります。
一定の年齢がきたら、客観的に判断をする検診はとても重要だということが分かります。
MCI を見つけるには、時折「新しいこと」「普段と違うやり方」「いつもと違う場所に行く」などをしてみることです。誰かと一緒にすることで、そのことが全く記憶されないことに周囲も気づくはずです。動くこと、人と付き合うこと、話すことが、認知症の予防にも、早く気づくことにも、進行を遅らせるのにも重要なことです。
早く気づくことの重要性を、改めて教えてください
MCI や軽度認知症の段階では、予防や治療法、今後の生き方などを自分で選び決めることが出来ます。病気だからといって社会から排除されたり、生き方を他人が決めたりしていいわけはありません。認知症になったら何もできなくなるわけではないし、人生が終わりでもない。自分らしく人生を終えるために、「早く知って自分の人生設計をする」「意思を表明する」「手立てを考え自分らしく生きる」これが新しい認知症観だと思います。
病気を知っても、手立てがないなら知らないほうが良いこともあるかもしれません。
しかし、認知症は手立てがあります。早期なら薬もあるし、対処法や進行予防プログラムなども確立されてきています。記憶できないならメモをすればいい。今はスマホをはじめ、たくさんの手段があります。
例えば、目が悪い人は眼鏡や老眼鏡をかければ生活ができます。眼鏡をかけている人が社会から排除されることはないですよね。同じように、世の中が認知症を受け入れ、足りない部分を補う眼鏡のような道具や対処方法があればいいのですが、まだこの道具に当たる部分が足りていないのが現実です。
だからこそ、MCIや軽度認知症のある人から、何に困っているのか、どんな状態なのかを聞いて、行政も医療関係者もそれを補う対策や道具などの準備に反映させ、誰もが生きやすい社会をつくっていくことも急務となっています。
家族の視点では、心の負担を軽減できます。
病気だとわかると受容することができ、行動の予測ができますし、専門医による対処方法を学ぶことで不安が軽くなったというご家族も多いです。できないこともあるけど、できることもあるとわかると、対応の仕方も変わります。
でも…ずっと一緒に生活している中で、同じことを何百回も聞かれるのは、家族としてはストレスになるのは当然ですよね。その時は、記憶のスイッチが入っていないので覚えていなくても仕方ないと理解していただいて、覚えさせよう・忘れないようにさせようではなく、覚えなくても分かるようにしておくなど、ちょっとした切り替えで、その心の負担を少しでも軽くできるといいなと思います。
本人も家族もですが、予防しようと頑張りすぎるとお互いが疲れてしまいます。100 パーセントの予防はできませんし、年齢とともに認知症リスクは高くなります。誰でもなりうる病気です。ゼロにはできないからこそ、できるだけ進みを遅くしていくことが重要です。本人も介護する側も、疲れ切ってしまうのではなく、少しでも自分でできることを増やしていきましょうと伝えたいですね。そのためには早期発見が重要なので、もの忘れ予防検診やもの忘れ外来を活用してください。
医師 山田病院認知症疾患医療センター長
薫風会山田病院内 認知症疾患医療センター長 竹中 秀夫先生に、認知症の検査や予防プログラムについてお聞きしました。
プロフィール
東京都出身、1977年に日本大学医学部 卒業、その後同大学附属病院、メニンガー記念病院などにて研修後、長谷川病院、日本大学付属板橋病院、江戸川病院などにて精神科診療に従事。2008年より山田病院にて診療を開始。2013年 同院 認知症疾患医療センターセンター長に就任し、現在に至る。
資格・所属学会
精神保健指定医、日本精神神経学会、精神科専門医、指導医
日本老年精神医学会
認知症に対する医療の現状を教えてください
現在は認知症に対する医療の大きな転換期にあると言えます。
医療の進歩により、早期に正確な診断が可能となっています。他の病気と同じように早期発見がとても重要ですが、もの忘れ予防検診の利用が増えたことにより、早い段階での気づきが可能となり、予防プログラムや治療法も整備されてきています。また、アルツハイマー病による軽度認知障害や軽度認知症に関しては新しい薬も実用化されています。
以前は、認知症予備軍の人に対しては、食事や運動などについてアドバイスを提供していましたが、その実践を支援するプログラムはほとんどなく、残念な気持ちでした。しかし、多くの調査や研究から認知症の予防に関する重要事項が明らかになり、同時に、各地の実践状況が報告され、それらを参考にして西東京市では昨年から予防プログラムが始まっています。
認知症疾患医療センターとは?
日本は超高齢化社会となり、年齢を重ねることにより病気のリスクも高くなり、もの忘れなどの認知機能の低下により生活が困難になっている人も増えています。このような大きな社会的課題に対して、東京都は、平成24年に12カ所の認知症疾患医療センターを配置。その後、各圏域の病院などに同様のセンターを50カ所以上配置し、当病院も平成25年に認知症疾患医療センターとして指定をうけ、西東京市と近隣4市を担当する専門機関として現在に至ります。
役割は大きく3つあり、
- 当事者の方とそのご家族のサポート
鑑別診断と初期対応をはじめ、専門医療相談、合併症への対応、行動・心理症状(抑うつ、徘徊など)への対応
- 各分野との連携
行政、医療機関、介護施設、地域包括支援センターなどのハブとなり、併せて認知症に関する情報提供
- 人材育成
かかりつけ医や看護師、介護士などの勉強会などを担当などです。
認知症の検査と予防プログラムについて教えてください
認知機能の低下は、3つのステージに分かれます。
- 加齢による認知機能の低下:認知機能の低下はあるが、生活には支障がない
- 軽度認知障害(MCI):加齢による場合より認知機能の低下はあるが、自立した生活が可能
- 認知症:認知機能の低下は進み、生活に支障が生じている。
ご本人やご家族の話は極めて重要ですが、それだけで区別することは難しく、何らかの客観的指標が必要です。もの忘れ予防検診などで認知機能の低下が疑われる場合は、専門的な検査をお勧めしています。
初期検査では、身体面の検査のほか、認知機能に関する簡易検査などを行います。これにより、認知機能に影響する身体疾患の有無、認知機能の概略を把握します。
次に、認知機能の低下が疑われる場合は、精密検査として、神経心理検査と脳画像検査をお勧めしています。
神経心理検査により、認知機能低下のレベルやその特徴を把握し、対応策の資料とします。
脳画像検査では、その低下の原因となる病気を把握し、認知症の場合であれば、病気に応じた治療法を提案します。
ひとことで認知機能の低下と言っても、原因によってそれぞれ特徴があり、より詳しく知ることで正しい対処や治療が可能となります。
認知症予防プログラムは、軽度認知障害あるいは認知症と診断された人を主な対象としたものです。
プログラムは複数回のセッションに分かれ、現在は7回を1クールとして実施しています。予防に役立つ情報の提供と活動の習得、さらにその実施、地域活動への参加をサポートしていく内容となっています。
このように、早期発見のための検診、正確な診断、そして進行を遅らせる予防プログラムまでが連続したシステムとして利用できるようになったことは大きな一歩です。
健康管理の一環として、体の健康診断と同じように、定期的に脳や認知機能についての健康診断を受けていただきたいと思っています。
検査と聞くと「悪いところが見つかったらどうしよう…」と不安になる人も多いと思いますが、早く知ることにより、いろいろな対策を一緒に考えるとことができます。日常生活でミスやもの忘れが増えたと感じたら、早めに検診を受けることやかかりつけの先生に相談することをお勧めします。
関連リンク
もの忘れ予防検診普及啓発を目的としたラッピングバスが走ります
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、広報プロモーション課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9804
ファクス:042-460-7511
